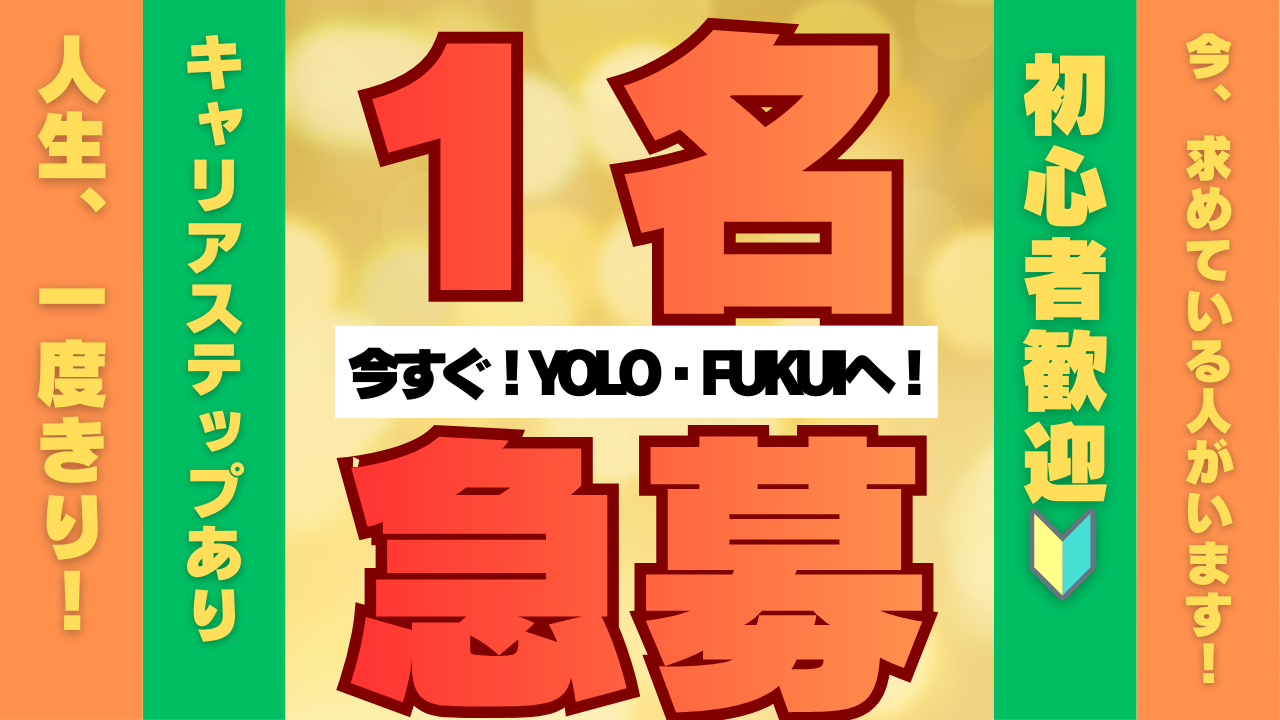YOLO日記
2021.02.02
節分の日
「鬼は~外! 福は~内!」
今日は節分。
(YOLOでも、昼食は恵方巻✧みんな黙々と無言でほお張る(笑))
節分が2月2日になるのは、124年ぶり( ゚Д゚)
日本は四季がありますしね、一年を二十四節気に当てはめて運用しようと思うとズレが生じてくる。
調整した結果、
立春の日が2月3日になるから
節分の日(立春の日)もズレる…ということらしい。
誰がいつどうやってそれを決めているのか…
少しググってみたら…
毎年計算した上で国立天文台が決めて、
毎年2月1日に翌年の暦が発表されるとのこと。
(なので、もう来年(2022年)は、日食が2回・月食が2回あるなんてことも分かっている!)
(^^)ご興味のある方は↓↓↓
https://eco.mtk.nao.ac.jp/koyomi/
こんなことをちょっと掘り下げるだけで、
誰かが自分の知らないところでいろんなことを決め、
自分の知らないところでいろんなことが動いているんだなぁ
…と改めて思う。
『2月3日が節分』、 そんな常識があっさり覆され“当たり前”になる(なっている)こともある。
それも気づかない間に…
今の「生活様式の変化」もそうかもしれない。
気づかない間に、いつの間にか違うレールに乗っているような。
“当たり前”は変化していくもの。
“当たり前”ってなんなんだ?…追求し続けるべし。
2021.01.29
強度行動障害!?
身体・精神・知的の三障害の支援に加えて、難病や強度行動障害となんでもござれ状態のYOLOです(^ ^)
以前の職場は身障者メインでやっていましたので、ここに来てより多くの経験をさせていただいています❗️
知的の方は、以前から触れ合う機会がありましたので、上手くやれてるかなと思っています。強度行動障害の方については… まだまだ体当たりの手探り状態ですね(^^;)
実は、従兄弟が自閉症でして、幼少期よく遊んでいたのです。『なんか別の世界観を持っているな』って思っていました。と言っても、当時は『なんか変わった奴だな』ですけどね(笑)
実際、支援する立場になりますと、彼がその世界観でしか生きられない風に生まれたなら、一般社会の価値観で生きることを強いられるってのはストレスフルでしか無いのだろうと考えた訳です。そんな精神状態な上に、更にストレスが重なって大爆発… と、行動(二次障害)に出るのだろうなと。
それらを踏まえて支援していく訳です。本人にとって介助者がストレスになっては木阿弥ですので、本人の価値観を尊重しなければ介助は出来ません。
心苦しいのが、その価値観が世間にとって不快と捉えられること。
まだまだ理解があるとは言えない現状ですので、方々から当事者に対して強い矯正(抑圧)の力が働きます。でもそれは、その人の人生を殺すものだと解って欲しいと願います。
ズレていたって意思のある一人の人間。彼らの常識からみたら、一般の方がズレていると言う、定型発達者(健常者)・非定型発達者(自閉症者)という表現が分かりやすいかもしれませんね。
我々にとってその突飛見える行動がどれほど迷惑なのかと、改めて考え直し、認めていく。
常識を押し付けて、一人の人間の人生を殺してしまってはいないかと振り返っていく。
画一的な価値観をアップデートしていくこと。多様な人間が生きやすい『社会モデル』は必要です。
行動障害は本人にとっての不快を訴える術であって、本人なりの行動で示しているだけ。
我々は、根底にある多大な抑圧を理解した上で、快・不快を考察していくこと。出来る限り不快(障害)を取り除くこと(社会モデル化)。本人は、感じた不快をより上手く他者に伝えるられるようになることが歩み寄りなんだと思います。
2021.01.18
大雪の中心で除雪を叫ぶ
いやー。降りました。
雪。
福井県(特に嶺北)では1メートルを超える雪がドーンと降り、交通マヒが起こるわ、あちらこちらでスタック、スタックの嵐。
私の家の前もすごいことになってました。
ワタシんちも大きい通りとまではいわないのですが、生活道路としては大きい道になるので(2車線あるのに生活道路)車の往来が激しい場所になります。また、駅や学校も近いことで人通りが激しい場所でもあります。
昔はすんなりと除雪が入っていたみたいですが、3年前にあった平成30年豪雪の時も今回も大雪後の4~5日後に除雪が入るという事態。
降ってすぐは車も出ることなどが頑張ればできるのですが、気温が上がると雪は溶けていくのでぐしゃぐしゃの状態になり、状態によっては雪の上に車体がのっかってしまいスタック(タイヤが空回り)状態になってしまうのです。
溶けていけばいくほどその状態は起きやすく、車で進むには限界が出てくるのです。
実際夜中に「助けてください」と駆け込んできたこともありました。
そんな中、○○役場の道路課に連絡をしたところ・・・。
「大きい道を優先にあけているので待ってほしい」といわれました。
なるほど。大きい道を空けることに専念しているから除雪が遅い。
ちなみにうちの地区を空けている業者さんはどこですか?と尋ねてみると、
「○○会社さんです」との返答が。
早速電話をしてみて、いつ頃に入る予定なのかを確認すると、
「あなたのエリアは○○第2基地局が管理しているので私たちが勝手に動くことが出来ないんです。早くしてあげたいんだけど、ごめんなさい。」との返答が。
また、「作業には基地局からくる図面を見ながら作業されており、優先する場所は鉛筆などで黒く示して各業者さんに送ってこられて毎日計画して行っているので」ということでした。
要約すると、除雪は各管理基地局がどこを除雪するかを基地局が行っており、その指示のもと動いているとのこと。
また、除雪車にはGPSが取り付けられており行動を監視されているとのこと。(30年豪雪の時にはGPSがついておらず、除雪車がどこにいるかわからないという事態もあったため、基地局が管理をするために約500台の除雪車に取り付けているみたいです。詳しくは福井県・市の除雪計画を参照してみてください。)
基地局の電話番号を教えてもらい改めて道路課に会社さんからの返答を伝えたところ、こちらから基地局に伝えるとの返答が。
お願いしますと伝えたうえで、こちらからも基地局の番号に電話をしてみました。
いつ頃除雪が入るのか、スタックする車も多いため、優先で開けることはできないのか?との返答に対し、
「除雪のタイミングとしては各業者さんにお願いしている部分なのでこちらではどうしようもない。」
「また、個人の方がこの番号をなぜ知っているのか?こちらではあなたの除雪している業者さんを教えることが出来ない」などを言われました。
理由として誹謗中傷や個人の要望を各業者さんに直接行かないようにするためとのことでした。
けど、ここで矛盾が生じています。
業者さんと話していた時には「基地局からの指示で私たちは動いている」と言われ、基地局からは「業者さんに除雪の場所は一任している」と言われていた。
ちなみに除雪のタイミングで家の前の除雪業者さんに直接今回のことを話してみると、苦い顔をされていました。また、ワタシんちの前の道についても「(優先で除雪することに対し)この道についてはわかります」と言われてもいました。
今回のことを通してわかったことは現場の方たちは一生懸命に業務を全うしているということ。
また、業者さんも除雪する順番に違和感を持っていながらも作業されているということ。
何日も作業員の方たちは帰れない、会社で仮眠をしながら現場に行く。
また、通常の業務も当たり前にある中での作業となればとてつもない肉体・精神面での配慮が必要なんだと思います。
また、○○役場の道路課と基地局との連携や基地局の判断というものに対して不自然に感じるところもありました。
道路課さんは丁寧に対応していただけた中で、基地局さんの対応はあくまで作業内容などをブラックボックス化することで自己の業務の円滑化に特化しているようにも感じました。
3年前の教訓が生かされていない。何も変わっていない。
その理由が見えたようにも思えました。
あくまで私的な考えや印象ですし、皆さんがどうとらえるかでまた変わると思います。
けども、あれだけの大雪。
日中通行止めにしてでも除雪することに特化すればこんな事態は防げたのではないのでしょうか?
実際、大雪後に日中除雪作業をあちらこちらで交通規制しているのにその言い分というのは正当な理由なのでしょうか?
業者さんには本当に感謝です。そして、これからも作業をお願いします。
雪は溶けてなくなってしまいますが、雪のことで起きた問題はいつまでも残ると雪国の先人たちはいわれております。
早く雪と同じように解消してほしいと思います。
2021.01.15
雪、とにかく雪
すっっっかりブログ書くのを忘れていました。
そんな余裕のない一週間でしたね…
寝ても覚めても、降り続ける雪!
3年前の豪雪を彷彿させる、大雪。
一晩、二晩であれだけ降るとまぁ焦りますね;
『車を出せない!』というスタッフも多数。(私も数日、動かせず)
そんな時でも生活は止まらず、私たち介助者は各利用者さん宅へ。徒歩でも、時間がかかっても、訪問させて頂きました。(みんなお疲れ様!!)利用者さんも、時間の調整等して下さった方もいます、ありがたい(;_;)
雪に限らず、コロナだろうとなんだろうと、サービス利用者の生活は止まらない。そのサポートをするのが私たちのお仕事です☆
とはいえ、車が使えない!となると中々に大変でした。
自分の車を出すために雪かきをしていたら、ご近所の方も一緒に雪かきをして下さり、無事出せるように!!
車を出せてからまだ道が凸凹の中、見事に亀の子スタックしましたが(汗)その時も、近くのクリニックの方々が気付いて雪をかいてくれたり、友人等々助けに来てくれた方もいて、
うわぁー泣けるー(;_;)皆さんすみませんありがとうーーー(;_;)
と思ってました…感謝です。ほんとに。無事、救出されましたマイカー(無傷)
福井良いとこ、みんな優しい…昼夜問わす、除雪車で作業をして下さっている皆様にも感謝です。
あれ、私助けてもらってばっかじゃん。
今回は助けてもらってばかりだったので、次の大雪・その他でも大変な時は、周りの方の手伝いを出来たら!と思います。
一旦、雪は落ち着きましたが、まだ1月です。天災は予告なく訪れます、2月も怖いなー…
度々、休みながら、この冬を乗り切りましょう☆
2021.01.07
ワクワク ワクワク
年明け、新たな出会いの予感が毎日現実になっています( *´艸`)
連日いろんなことが起こっている✧✧✧
少し前から関わってきた方のサービスが開始されたり、
「明日から!」という急なご依頼も対応させて頂いたり。
サービス外でのサポートも。
本当に何が起こるか分からない毎日にワクワク✧
昨日は、YOLO事務所でラジオ収録がおこなわれました!
場所を提供させていただいただけなんですけども、
事務所に機材が運ばれてきてセッティングしている様子を感心して見ていた…
と思いきや、まさかの出演!Σ(・ω・ノ)ノ!
でも、あっという間の時間で、
逆に時間の中に収めることが難しく感じました(^-^;
そんな中…
整ってきた制度やサービスの、整ってきたからこその弊害や、
縦割りの効率性の一方で違う敷地に行った後にはフォローしたくてもできない現状
(それによって取り残される当事者)も感じます。
ワクワクがフワフワにならないよう、
浮足立たないよう落ち着きは維持しながら。
春にはちょっと楽しいことも企画しています(*^▽^*)
(4月6日=ヨロの日 と命名し、その周辺で)
年明けからコレだとどんな彩りの一年になるでしょうね~♪